当院のめまい外来は予約制となります。
初めての方はまず一般外来を受診いただくことになります。初診時は検査に時間を要しますので順番に関わらず午前は12:00、午後は17:30までに受付にお越しください。
めまい外来|練馬区の耳鼻咽喉科なら高野台いいづか耳鼻咽喉科へ
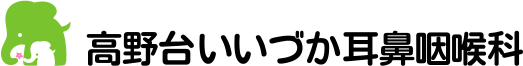
東京都練馬区南田中3-7-28 1階
西武池袋線「練馬高野台駅」徒歩3分
desktop_mac順番取りネット予約 event_noteWEB問診 よくある質問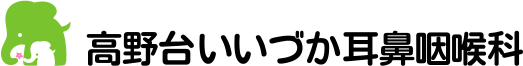
東京都練馬区南田中3-7-28 1階
西武池袋線「練馬高野台駅」徒歩3分
desktop_mac順番取りネット予約 event_noteWEB問診 よくある質問当院のめまい外来は予約制となります。
初めての方はまず一般外来を受診いただくことになります。初診時は検査に時間を要しますので順番に関わらず午前は12:00、午後は17:30までに受付にお越しください。
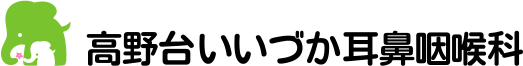 |
|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中3-7-28 1階 |
|---|---|
| 電話 | 03-6913-3366 |
| 最寄駅 | 西武池袋線「練馬高野台駅」より徒歩3分 |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科・アレルギー科 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | remove | ▲ | remove | |||||
| 15:00~18:30 | remove | remove | remove | |||||
| ▲~13:00まで 休診日木曜・土曜午後・日曜・祝日 混雑状況について | ||||||||